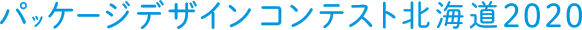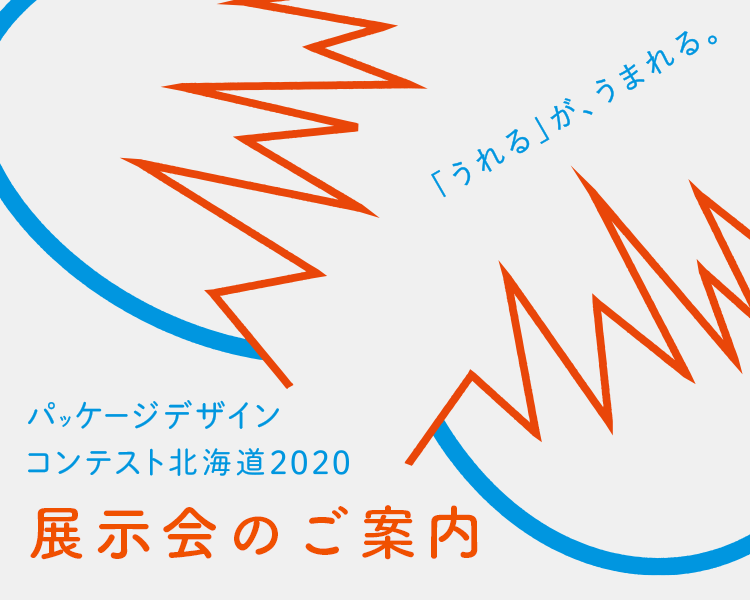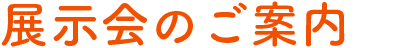展示会のご案内
質疑応答
受賞者と企業からの質問に、
専門家がお答えします。
答えていただく方々

- 審査委員長
- 白本 由佳 氏
- アートディレクター
グラフィックデザイナー
株式会社SHIRO代表

- 審査委員
- 岡田 善敬 氏
- グラフィックデザイナー
アートディレクター

- 審査委員
- 佐藤 健一 氏
- アートディレクター
AMAYADORI代表

- 弁護士・弁理士
- 川上 大雅 氏
SDGs、AI、コロナ禍。時代が急速に変わっている中、今後パッケージデザインを進めるにあたり、特に考えなければいけないことなどありますか?
特にここ1年でサスティナブルであることをパッケージに求められることが本当に多くなり、今まで当たり前だったことを考え直す機会も増えました。
本当に必要なものかどうか再検討をしたり、新しい素材を探したり、今までとは少し違った流れになってきています。ですが、それは近いうちに当たり前のこととなっていきます。
ですのでその流れの中で新しい方法やデザインを生み出していくことが重要になっていくのではと思っています。
閉じる
デザインする上で、色使いはとても重要かと思いますが、色数を多くするとどうしても、まとまらないなと思うことが自分自身よくあります。色を積極的に使いつつも、世界観を統一するという観点で意識していることはございますでしょうか?
同じトーンの色を使ったり、色以外のデザイン要素を極力シンプルにするなどいろいろな方法はあるかと思いますが、それぞれの目的によって方法は変わってくるかなと思います。
まずは全体の世界観のイメージを作り上げてから、その世界観に合う色は何色で何色必要なのか、など整理しながら色の選択をしていくようにしています。
回答を見る
商業デザインは企業側の選択眼も大事になってくると思います。企業側の決定者へ直接プレゼンできない場合など、工夫や気をつけている事などありますでしょうか?
またいわゆる鶴の一声などで自分の意思とは違う方向性に進んでしまった場合、どのような対応をされていますか?
まずは、ヒアリングをとても大切にしています。クライアントの想いをカタチにしていくのが僕のスタイルです。
プレゼンはなるべく決定権のある方にできるような関係性を構築するようにしていますが、それが出来ない場合は、わかりやすく企画書をつくるか、担当者へしっかり想いをつたえます。
鶴の一声で自分の意図と反する方向性に進んでしまう場合ですが、まずは先方の臨んでいる方向性で修正をしてみます。その上で自分なりの解決策を提案するように心掛けています。
回答を見る
デザインやクリエイティブにおいてコミュニケーションとビジュアル表現の両立は一つの課題かと思うのですが、岡田さんのデザインはどちらも長けていると感じます。デザインする上で、コミュニケーションとビジュアル表現を両立するために心掛けていることはありますか?
コミュニケーションとビジュアル表現を分けて考えた事はないかもしれません。
コミュニケーションのためのビジュアルだと捉えております。まずは何を伝えたいかを見つけて、それからどう伝えるかを考えます。それが同時に思いつく時は、うまくいく確率が高い気がします。
回答を見る
同コンテストで実際に商品化されているかと思いますが、商品化実現へ苦労した点と、商品化実現に向けてアドバイスがあれば教えてください。
ほんだ菓子司様の「さつまいもとりんごのパイ」ですが、クライアント様のご理解のお陰でほとんど苦労しませんでした・・・。強いて言うなら、さつまいもの生産者さんの顔写真と紹介文を載せたいというご要望がありましたが、パッケージは情報を詰め込むものではないということをご説明し、その替わりにミニリーフを作って箱に入れることを提案し実現しました。箱は捨てられますが、ミニリーフだと取って置いてもらえる確率が上がりますしね。
商品化実現に向けてですが、お客様からのご要望をお聞きした上で、やるべきこと、やるべきではないことを見極めて最善策をご提案することだと思います。一番大切なのは商品が1つでも多く売れることなので、そのために必要な変更は前向きに検討しつつ、デザインが壊れてしまうような要望に関しては、それをするべきではないとしっかりと説明すること、できれば代替案をご提案できるとさらに良いと思います。
回答を見る
「売れるパッケージ」と「いいパッケージ」は違うと思っているのですが、売れるパッケージとして特に気をつけている事などありますでしょうか?
クライアント様とそのお客様がいる以上、「売れるパッケージ」が「いいパッケージ」だと思います。とはいえ、デザインが素敵な方が断然良いですよね。笑
パッケージに限らずですが、買ってくれる方の気持ちに立つことを重要視しています。デザイナーの自己満足なデザインになっていないか、不親切な部分が無いか、その上で、デザイン上のそぎ落としや、エッジを残すために何ができるかを考えます。
回答を見る
パッケージデザインをする上で、シンプルな中でも、その商品としての特徴を入れる必要があると思うのですが、私の場合付け足した感というかこれはいらないという要素を入れてしまうことがあります。佐藤さんがデザインされた商品はその辺りのバランスがよく、デザインと商品の佇まいが「しっくりくる」というふうに感じました。何か意識してデザインしていることはありますか?デザインの前段階のヒアリングなどでも構いません。整理の仕方がありましたらお聞きしたいです。
お褒めのお言葉ありがとうございます!
買ってくれる方の気持ちに立つこと=客観的になること。あとは、どんなお客様をメインターゲットにしているのかを打ち合わせでしっかりと聞くようにしてます。デザインのそぎ落としは時に勇気が必要ですが、少しだけ「なんだろう?」と思ってもらうくらいの方がむしろ印象に残ると思います。
その上で「なるほど!」と思ってもらうこと。「?」から「!」の流れを作ることができると良いですね。
回答を見る
商品名も含めた提案の時、商品名・デザインあるいはコンセプトなど何から考えることが多いですか?また、商品名のコピーなどを外注するかどうかは何を基準に判断されますか。
商品名から含めて総合的に提案する場合は、基本的にはクライアントさんとの打ち合わせの中でコンセプトとイメージををすり合わせることから始めるパターンが多いです。商品の様々な情報(ターゲット、価格、売り場、競合とのバランスなど)をヒアリングして今回の商品にとって何が「核」となるのかを探していく作業から始めます。ある程度コンセプトが固まってきた段階で、次の段階(デザインなど)を進めていきます。
コピーに関しては専門性が問われることも多いですし、言葉の質と幅は大事だと思っていますのでコピーライターさんにお願いすることが多いです。
コンセプトからでしょうか。同時にデザインやネーミングを思いつくこともあります。コピーに関してディレクションはしますが、基本的にコピーライターにお願いすることが多いです。
その商品名やデザインで、何を伝えたいのか、何を知って欲しいのかの優先順位をしっかりと決めること。クライアントの情熱があればあるほど、あれもこれも伝えたいと思うのは当然なのですが、それをすると結局散漫なデザインになるので、一番伝えたいことは何かをクライアントとお話して決めるようにしています。
コピーに関しては(予算がしっかりあるのが前提で)ほぼコピーライターさんに依頼しています。言葉のことは言葉のプロにお任せした方が絶対に良いのができるので。
回答を見る
情報を集める段階では、企業とのコミュニケーションはどの人達ととりますか。(担当者のみと話し合う、事務の方も話す、工場の方達とも話す等)また、どのようにとりますか。(その場での立ち話程度、会議室に来てもらって話す、個人的な連絡先を交換して話す等)
そのような場合は基本的に打ち合わせの機会を作っていただきます。
基本的には担当者の方とのやりとりが多くなりますが、他の部署の方の情報も必要であると思えば、そのような方を打ち合わせの場に呼んでいただいたり、事前に情報をいただくというようなこともあります。必要であれば、現場(お店や工場など)を視察しインタビューすることもあります。
ケースバイケースですが、なるべくたくさんの方とコミュニケーションをとればそれだけ深くクライアントのことが理解できると思っています。
その商品、クライアントの規模によってケースバイケースです。代理店様が間にいる場合は、クライアントと直接やりとりしない時もありますし、直クライアントの場合でも、大きい企業であれば打ち合わせは担当者と行い、決裁者=社長とは会わないこともありますが、できる限り決裁者としっかりと顔を合わせて打ち合わせをするようにしています。
回答を見る
同じデザインでシリーズ展開をする場合には何か注意されている点はありますか?
シリーズ展開をする場合に気をつけることは、1つのブランドとして認識できている状態でそのシリーズの区別がちゃんとできているかという点です。色やデザインの違いでそれぞれのシリーズの特徴を出していても、全体でみたときにバラついた印象になってしまわないよう、ブランドとして同じメッセージを伝えているということが大事かなと思います。
最初の時点で、変える部分と変えない部分を考えておく事でしょうか。
初めからシリーズ展開することが分かっている場合は、レイアウトや配色など展開のしやすさを重視すると同時に、同じ商品に見えないようにしっかりと区別できるかどうかも重視しています。双子に見えてもダメだし、従兄弟に見えてもダメで、仲の良い兄弟を目指す感じでしょうか。笑
回答を見る
複数案を提案する場合にはどのような点に気をつけていますか?ひとつの仕事に対して複数案のご提案をされているかと思いますが、ターゲットやコンセプトがまったく違う方向の案を提案するのか、ターゲットやコンセプトは同じだけどデザインが違う3案を提案するのか?など、何かあれば教えてください。
基本的にターゲットやコンセプトは事前にすり合わせていることが多いので、デザインの方向性として案を出すというパターンがほとんどです。同じターゲットやコンセプトであってもデザインのアウトプットの仕方で伝わり方が違うのでその方向性の違いということで案を出します。ターゲットやコンセプトを反映した案を何案か提案した上で、こちらからもっと違うコンセプトの方がよいのでは、と思うことがあればそれらの案も追加して提案することもあります。
まずは大きくコンセプトの異なる案を出すケースが多いです。
後者となります。商品がしっかりしていれば、ターゲットやコンセプトは変わることはありません。その範囲の中で、「インパクトのあるもの」~「定番」~「親しみやすさ」など、デザインの振り幅を持たせて複数案提案しています。ただのバリエーションに見える提案はしないように気をつけています。
回答を見る
デザイナーとして常に心掛けるべきこと、心に留めておられること、ルーティンなど日常的に心掛けておられる仕事の流儀はございますでしょうか。
クライアントの求めているものをなるべく理解しそれを表現することです。それに加えてクライアントが想像しているもの以上のデザインや考えを毎回提案できるようにしたいなと思っています。
クライアントの想いをカタチにすることです。
相手の立場に立つこと、気持ちを想像し思いやることです。(出来ていない時ももちろんあります!人生日々勉強です・・・)
回答を見る
人生で最も大切にしている価値観を教えてください。
家族と健康を大切にしたいと思っています。
忙しくて第一優先にできない時もありますが、大切にして生活したいと思っています。
人生で最も大切にしている価値観・・・考えた事はないですが、なんでしょう???
家族との時間は大切にしています。
何事にも感謝することです。そうすれば、どれだけ自分が恵まれているのかを知ることができ、さらに感謝できる人生になると信じています。
回答を見る
デザインを評価するときに、デザイン単体の見栄えやアイデアが主な評価基準になると思いますが、他にどのような点を重視されますか?例えば生産のしやすさ(色数、輸送しやすい形態、紙箱でも無駄の出ない形状など)売り場に置かれたときを想定した見栄え、陳列時の機能性(品名の読みやすさ等)使用する場所での見栄え、使用時の機能性(残量の見やすさ等)
通常の審査会などにおいてはそこで得られる情報でしか判断することができないので、基本的には見える部分(アイデアやデザイン)で評価をしています。本来は機能、素材、価格などを総合的に評価できることがベストだとは思いますが、その点においては審査会で探ることができないので、評価基準とするのは難しいなと感じます。
ですが、今回のパッケージデザインコンテスト北海道2020の審査においてはクライアントさんと商品の情報、オリエン内容が公開されているので、そのオリエン内容に沿った上でよいデザインとして表現できているかどうかを判断することができました。ですので、オリエン内容をクリアできているのか、現実的なものなのか、という点は評価のポイントになったと思います。
今回のようなコンペでは機能やコスト面は重要なポイントになりました。
コンペによっては「新しさ」が評価の軸になる場合もあります。
個人的には「いままでない」「ありそうでない」・・・みたいなものにドキドキさせられます。
今回のコンテストで考えると、クライアントからの要望や課題がはっきりしていたので、そこがしっかり考えられているかも見させていただきました。商品化することが目的である以上、完成度が高くてもコスト度外視だったり、クライアントの課題をクリアできていなかったりすると商品化できないので、実現性の高さも重視しました。
回答を見る
デザインのアイデアで詰まったときどうされていますか?参考までに教えて下さい。
時間を決めて考えるようにしています。
短い時間で集中して考える方が私には向いているので今日の何時までに絶対何案つくる。と自分で決めて
その間は頭と手を動かし続けるというようなやり方をしています。
信じて考え続けます!
ケースバイケースではありますが、
1.あきらめて家に帰る(お風呂、トイレ、寝る前に思いつく時が多いです。)
2.色んな本やWEBを参考にしてとことん粘る
3.気分転換にコーヒーを買いに行く
のいずれかでしょうか・・・。
回答を見る
普段お仕事をされていて、クライアントからデザインのコンセプトをくつがえすような修正指示をもらった場合どのように対処していますか?徹底して自身の考えを説得されますか?(デザインの理想・商品の作り手側の理想・売り手の理想は必ずしも一致するとは限らずデザインの文化価値をとるか、営利を取るかなど常に考えさせられてしまいます。)
事前の打ち合わせにおいてコンセプト、目的、イメージの共有はある程度しているというパターンが多いので、180度くつがえされるようなことはあまりないです。
ですが、デザインの要望を全て反映すると表現としておすすめできないという場合もあります。その場合は先方が納得していただけるような理由をお伝えしたり、資料を作ってお話をするというようなこともあります。
ヒアリングをしっかりして進めますので、あまりコンセプトをくつがえされるようなことは少ないのですが・・・そうならないようにコミュニケーションをとるのが一番です。
ただ、そういう状況になった場合は、まずは素直に指示通り修正してみます。
その上で自分なりの解決案もつくり提案します。
そうすることで、1つでも多く売れる可能性が高くなると納得が出来れば修正します。
それをすることでデザイナーから見たらダサくなっても、自分とは違う視点、気づかなかった視点でクライアントが考えた結果であれば受け入れることが多いですね。もちろん、さすがにそれはちょっと・・・と思う場合はしっかりと説明をしてお考えを改めてもらうこともありますし、そもそもそれを作る必要があるのか、という段階から話をすることもあります。
回答を見る
ターゲットが女性である商品のデザイン依頼も多いかと思います。異性がターゲットの場合、どのように考えデザインしてますか?
身近な人の気持ちを想像して考えます。
弊社の女性スタッフにデザインをお願いします(笑)。機能するデザインを作るためには、自分では手を動かさないという選択も必要です。得意な人にやってもらった方が絶対に良いですし。ただし、自分で考えて、自分で手を動かさねばいけない時もあるので、その場合はターゲットを漠然と捉えずに、自分の大切な女性の顔(妻とか母とか)を思い浮かべてデザインしています。あとは、作ったものを妻(デザイナー)に見てもらって意見を聞くこともあります。
回答を見る
地元で仕事を切り開くためにどのような『心のあり方』でお仕事に取り組んでいらっしゃるのか、そして、目覚ましいご活躍をされてながらも、あえて地元で働き続ける理由を教えていただけたら幸いです。
僕も自信はありません。
いただいた仕事を毎回全力でやるしかないですね!
印刷会社なら、下版する最後の最後までこだわることもできるはずです。同じ印刷会社のデザイナーとしてがんばりましょう!
ご質問者の様に東京での経験がなく、札幌で仕事をするのが通常のため、お求めの返答ができるかわかりませんが・・・。「心のあり方」で言うと、クライアントの課題を解決するために仕事をしていると考えているので、場所を意識したことはあまりありません。自分の好みでデザインしないことだったり、仕事である以上は賞を獲ることを最大の目的とはしないことだったり、そのあたりの考え方は、働く地域は関係ないことだなと、ご質問いただいて改めて実感することができました。ありがとうございます!
確かに東京と地方だと、デザインへの意識の高さや需要は違うかもしれませんが、クライアントと一緒に課題を解決した時のみんなの笑顔だったり、いただいた感謝の言葉のうれしさは、クライアントや仕事の規模は関係ないと感じています。むしろ、東京での色々なご経験が地元でかならず役立つと思います!どうか自信を持ってください。
2つめの質問は(目覚ましい活躍はまだまだできていませんが)単純に生まれ育った北海道が大好きだからです。なので、自分にとってはそれは「敢えて」ではなく「自然なこと」なのです。
回答を見る
デザイナーからの問い合わせや質問で1番多いことはなんですか。
実現したいデザインが既存のデザインに近いような印象がある場合や、何らか他のコンテンツを使用(引用)することを考えているときによくご相談をいただきます。「著作権的にちょっと気になって・・・」とか「商標的にちょっと気になって・・・」とか、「ちょっと気になって」の段階でご相談をいただける場合はすんなりと解決していく印象です。
いただいた相談に対して、できる限りデザイナーの意向は尊重したいなと思いつつも、そのままGOサインを出すことが難しいことも正直よくあります。それだけに早めの相談が大事かなといつも思います。
回答を見る
ショップ名や商品名で商標を取得したいというお客様がいらっしゃいます。ネーミングのみで取得する場合とネーミングと意匠をセットで取得する場合があるようですが、どのような意図で使い分けるのが良いのでしょうか?
丁寧に行うとしたら、「ネーミング」「ロゴマーク等の意匠」「ネーミングと意匠をセットした形」、それぞれ申請を行う方が良いことになります。
他方で予算もありますので、実際の場面では、「できる限りよく使うパターン」から優先的に取得を考えていきます。また、意匠のリニューアルの可能性や頻度、ネーミング、意匠それぞれの商標取得可能性の高低なども考慮した上で、どういう出願が良いか使い分けていきます。
回答を見る
デザイナーが事前に類似デザインの有無を知る方法はありますか?また類似したデザインはどこまでがアウトで、どこまでがセーフかを測る基準はありますか?
商標や意匠に関しては、J-PlatPatという日本のデータベースを最低限見ておく必要があります。また、近年では世界中どこから指摘が来るかわからない時代ではありますので、WIPOのGlobal Brand Datebaseや、Global Design Databaseも確認しておく必要があります(使いこなすのは少し難しいですが)。
もっとも、商標登録、意匠登録されていないデザインも世の中にはあふれています。こうしたデザインを含めて考えると、類似デザインの有無をくまなく調べることは難しいというのが現状です。
また、デザインの類似に関して裁判例の集積からくる基準めいたものもあるにはあります。
ただ、基準といっても結局は「似ている」というある種感覚に基づくものを言葉にしたものにすぎないですから、出願の場面や裁判の場面で「あれ?そうなの??」となることも良くあって、判断にはいつも悩みます。
回答を見る
中小企業がデザイナーにパッケージデザインを依頼する場合に知的財産を含め注意すべき点を教えてください。
デザインのイメージを伝えることは大事ですが、そのイメージが既存のパッケージを意識したものとなる場合には後から苦労します。完全なオリジナルというのは難しい時代になってきているとは思いますが、それでもできる限りのオリジナリティは追及してください。オリジナリティを追及することが知的財産権におけるトラブルを防ぐことにもつながります。
回答を見る
中小企業もしくはデザイナーが契約書を作成する際、最低限盛り込むべき事項を教えてください。
当たり前の話かもしれませんが、お金と期限と仕事の内容を決めましょう。立派な契約書の書式を持っていてもこれらが空欄のままになっていて、肝心な時に困ることが意外とあります。また、知的財産権関係では、デザインの著作権等権利関係の帰属を決めておくこととデザインの使用範囲を決めておきましょう。「あれ、思ってたのとなんか違う・・・」ことからトラブルは始まっていきます。
回答を見る
中小企業が自社商材のパッケージデザインをデザイナーに依頼した際に当事者間で契約書を作成しない場合、両者それぞれに将来どういった不利益が考えられますか?
お互いの考えていることが合致していない場合には、お互いそれぞれに不利益が生じます。考えていることが一致していて全て円満に終わるのであれば契約書は作る必要がありませんし、「契約書」という書類にこだわる必要もありません。双方が後から困らないような記録が残っていることが非常に大事です。他方、記録の残し方が不十分であったり、肝心な部分が記録に書いてなかったりすることもあります。通常考えうる決め事を残す意味で契約書というフォーマットは使い勝手が良いと思いますので積極的に作っていくと良いです。
回答を見る
契約書を作成したことがないのですが、参考にできる契約書のひな形を教えてください。
インターネット上には有料無料含めたくさんの契約書ひな形が存在しています。これらを一つに絞らず何通か読んでみることをおすすめします。その上で必要なこと、決めたいことをイメージして専門家に依頼するのが良いかと考えます。
回答を見る
デザイナーにデザイン料を支払ってデザインしてもらったパッケージデザインの一部をデザイナーの了解を得ず、変更して利用することは可能でしょうか?
契約の内容、また、「一部」をどの程度「変更」するのかにもよりますが、一般的には難しいと考えます。かかる行為はデザイナーとクライアントとで当初決めた「利用範囲」を超えることが多いと考えられるからです。
回答を見る
作成したパッケージデザインの権利保護に関して、著作権と意匠権ではどのような違いがありますか。
意匠権は登録しない限り発生しませんが、著作権は登録しなくとも発生します。他方、著作権侵害に基づき何かを請求する際には「偶然一致した」というのではなく「真似した(依拠している)」ことが必要となることが多いですが、意匠の場合にはこうしたことは求められません。そのほかにも違いはありますが、大きく違いがあるのはこの点です。
回答を見る
商品名やロゴの商標登録及びデザインの意匠登録はそれぞれいくらくらいかかりますか。
商標登録に関しては、特許庁宛費用が出願時に12,000円(1区分)からかかりまして、登録料が28,200円(1区分・10年)です。意匠登録に関しては、特許庁宛費用が出願時に16,000円かかり、登録に関しては年金として毎年8,500円(第1年~第3年)ないし16,900円(第4年~第25年)がかかります。弁理士や弁護士に頼む場合にはこれに別途費用がかかります。
<参考>
・経済産業省特許庁ウェブサイト 産業財産権関係料金一覧
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
回答を見る
今後、契約書や知的財産について相談したい場合、何処に問合せをすれば良いですか。
知財総合支援窓口(INPIT)https://chizai-portal.inpit.go.jp/、各地の弁護士会、弁理士会の相談窓口などが考えられます。もちろん私宛に連絡をいただいても大丈夫です。
<参考>
・INPIT北海道知財総合支援窓口
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/hokkaido/
・北海道弁護士会連合会
http://www.dobenren.org/
・日本弁理士会北海道会
https://jpaa-hokkaido.jp/
回答を見る