特許になる発明とは?
-
特許法上の発明であるか
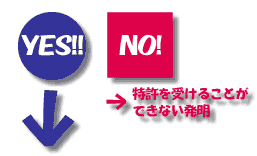
-
産業として実施できるか(特許法第29条柱書き)
特許を受けることができる「発明」であるためには、まず第一に、産業として実施できなければなりません。これは、ただ単に学術的・実験的にしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の目的が達成できず、保護する価値がないからです。
特許法における「産業」は、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、運輸業などの生産をともなわない産業もふくめた広い意味での産業を意味します。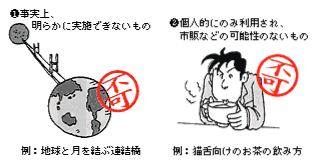
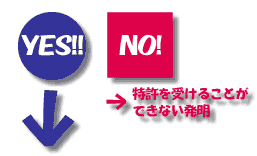
-
新しいかどうか(特許法第29条第1項)
特許を受けることができる「発明」は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。すでにだれもが知っているような発明に特許権という独占権をあたえることは、社会にとって百害あって、一利もないからです。
特許法では、次の発明の場合に「新しさ」がないとして特許されません。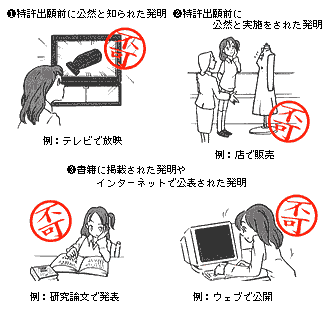
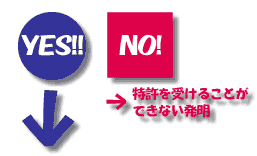
-
容易に考え出すことはできないか(特許法第29条第2項)
従来技術をほんの少し改良しただけの発明のように、だれでも簡単にできる発明については、特許を受けることができません。
科学技術の進歩に貢献していない自明の発明には特許権をあたえるほどの価値がありませんし、簡単な発明でも特許権が認められるようになると、日常的に行われている技術的な改良についても次々出願しないと別の人に特許をとられてしまいかねず支障がでるからです。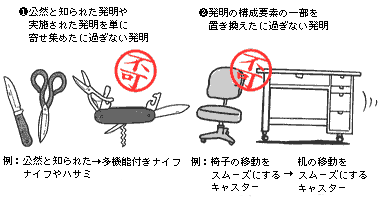
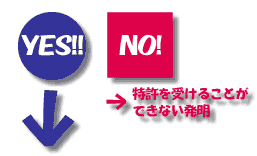
-
先に出願されていないかどうか(特許法第39条及び特許法第29条の2)
別々の発明家が同じ発明を同じ時期に完成して、同時に特許出願をする場合がよくあります。
この場合、わが国では、先に発明を完成した者にではなく、先に特許庁に出願した者に特許をあたえています。
これは、どちらが先に出願したかの方が判断し易く、いち早く発明を公開しようとした者を保護しようという特許制度の目的にも沿っています。
このように、同一の発明については、先に他人に出願されてしまうと特許を受けることができなくなりますから、発明が完成したら、できるだけ早く出願することが大切です。
※なお、同日に出願した場合は、時刻は問われず、協議で決めます。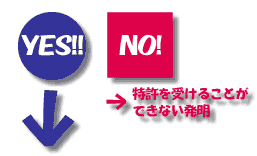
-
反社会的な発明ではないか(特許法第32条)
国家社会の一般的な道徳や倫理に反する発明や、国民の健康に害をあたえるおそれのある発明は、
たとえ産業として実施できたり、新しいものであったり、容易に考えだすことができないものであっても、
特許を受けることができません。たとえば、紙幣偽造機械、金塊密輸用ベスト、アヘンを吸う器具などは特許を受けることはできません。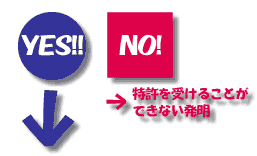
-
明細書の記載は規定どおりか(特許法第36条及び特許法第37条)
特許を受けるためには、具体的にどのような発明をしたのか、他の人が読んで理解できる程度に、発明の内容を明らかにする必要があります。
発明の内容は教えられないが、権利だけは欲しいというのは認められません。
また、特許を受けようとする発明について、権利を求める技術的な簡潔明瞭に定義する必要があります。
これらの要件を満たしていないと、出願書類の記載に不備があるものとして特許を受けることができません。
これは、発明を公開したことに対する代償としてあたえられるという特許制度の趣旨に反しますし、発明を正確に把握できなければ、特許の審査や権利侵害の有無の判断もできなくなるからです。
発明が完成したからといって、すべての発明が特許を受けられるわけではありません。
「特許」とは、「特許法によって、特許権をあたえること」をいいますので、特許を受けるためには、特許法で定める「特許が受けることができる発明」の条件を満たす必要があります。

