道具の発明・発見の歴史
-
200万年前
石器

石器は人類が一番始めに作った道具です。最初、石をそのまま道具として使っていましたが、やがて石を打ち砕いてできる鋭(するど)い部分を加工して、ナイフややりなどの先端(せんたん)に付けるようになりました。
さらに約1万年前には、石を砂などで磨(みが)き、おのやくわなどとして使うようになり、狩(か)りだけでなく農業や牧畜(ぼくちく)の道具として使われるようになりました。 -
50万年前
火
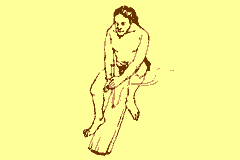
人類は誕生した頃(ころ)から、雷(かみなり)や火山の噴火(ふんか)によって起こった火を利用していました。そして50万年前には、火を絶やさない方法を発見し、偶然(ぐうぜん)、火を起こす方法を発見したのです。 火の発見は、夜を明るく過ごせたり、寒い土地にも住めるようになったりと、人々の生活を大きく変えました。
-
1万年前
土器
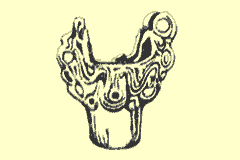
現在、一番古い時代の土器が発見されているのは、日本の縄文(じょうもん)時代のものです。土器は、土を粘土(ねんど)のようにこねて形をつくり、700~800度の温度で焼きあげたものです。 そして土器は食物を貯えたり、物を煮るために使われていました。また、神への供え物を入れるために使われたり、お墓に一緒に埋められたりしました。
-
紀元前3500年
車輪
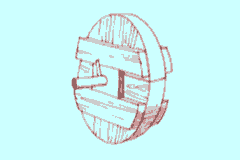
人類の祖先は、倒(たお)れていた木がそりの下で転がり、そりが軽く運べることに気づきました。これが「ころの原理」です。 その後、今から約3500年前、何枚かの板を組み合わせて円形にし、金具で止めた最初の車輪を発明しました。車輪は荷車などに使われ、それから滑車(かっしゃ)や歯車などに応用され、乗り物だけでなく、産業の発展の基となりました。
文字
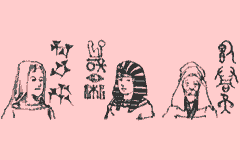
古代の人々は伝えたい情報を絵に描(えが)いて表していました。 絵は文字へと変化し、紀元前3500年にはメソポタミアで楔形文字(くさびがたもじ)が生まれました。紀元前3000年にはエジプトでヒエログリフという文字が、紀元前1500年頃には、中国で甲骨(こうこつ)文字と呼ばれる亀(かめ)のこうらや牛の骨にきぎむ文字が作られ、これが変化し現在私たちが使っている漢字になりました。
-
紀元前2世紀ころ
紙
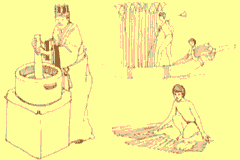
紀元前2500年頃のエジプトでは、パピルスという草のくきを縦横に編んで紙に似たものを作っていました。 中国の歴史書である「後漢書」によると、西暦105年に中国の蔡倫(さいりん)という人が紙を作り和帝に献上したとされています。 このため、紙の発明者は蔡倫であると言われてきましたが、近年の考古学分野等の発展に伴い、紙は既に紀元前2世紀頃から中国で作られていたことが分かっています。 蔡倫は、製紙法について改良を重ね、木の皮や絹のくずなどを砕(くだ)きドロドロに水にとかし、これを薄(うす)く伸(の)ばし乾(かわ)かして、質の高い紙を作ったと考えられています。
-
1000年ころ
羅針盤
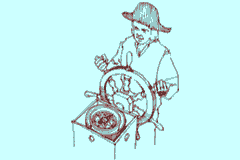
中国では、紀元前300年頃から磁石が南北の方向を示すことは分かっていました。 11世紀ごろには磁石の針を水中に浮(う)かべ方向を知る方法が、中国からアラビアをへて船乗りの間で広まりました。 しかし、船のゆれで水がこぼれて役に立たないため、1560年ごろイタリアで水平に磁針を保つ宙ずり式の羅針盤(らしんばん)が作られました。そのおかげで、陸の見えない所も航海できるようになり15.16世紀の大航海時代を迎(むか)えたのです。
-
1454年ころ
活版印刷(かっぱんいんさつ)
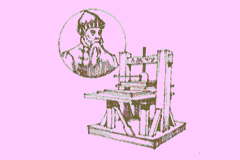
7世紀の中国では、板に字をほって墨(すみ)を付け上から紙を押すという木版印刷が行われていました。 その後同じく中国で11世紀に、一字ずつバラバラにして動かせる活字をつくり、活字を組み合わせて文章をつくり印刷する活字印刷という技術が発明されました。 その後15世紀に、ドイツのグーデンベルクはこの活字を鉛(なまり)で作り、当時のぶどうしぼり機で紙を押して印刷する機械を作りました。
-
1945年ころ
コンピュータ
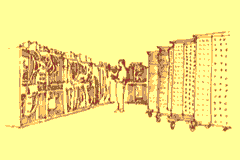
世界初のコンピューターは、1945年にアメリカでつくられた電子計算機です。 しかしこれは大量の電力を使い、巨大だったため実用的ではありませんでした。 その後それまでのコンピューターの機能が、1センチ四方に何個も入っている高性能な「IC」というチップが開発されました。 そのチップの開発により、コンピューターはとても小さくなり、家庭で使われる電化製品の中にも組み込まれるようになりました。

