商標制度
-
商標制度の意義
たとえば、ヘッドホンカセットに「ウォークマン」のマーク(商標)がついていたので、安心して買ったところ、実はソニーと無関係の会社が勝手に真似をした偽のマークだったとしたら、そのマークを信用して買った人の利益が害されます。 一方、ソニーの方も、たとえば、その偽の商品の品質が劣っていた場合には、ソニーの信用を失い、会社のイメージを落としてしまいます。また、偽の商品の品質が良かろうと悪かろうと、多くの時間とお金と労力をかけて有名にした商標を他人によって安易に真似をされたら、その損失は多大であるといえます。 そうしたことがないように、商標を保護する目的で定められたのが商標法です。
-
商標の存続期間
特許法などでは、発明の保護と利用を図るということから、一定の期間特許権者などに独占排他的な権利をあたえますが、その期間が過ぎれば、一般の人に開放して社会の共有の財産とします。 しかし、商標法では、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るものですから、特許法などのように存続期間を限る必要はありません。 むしろ、存続期間を限るというのは、長年にわたって蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に反することになってしまいます。 その一方、全く使用されていない商標などは保護する必要がないといえます。 そこで、商標の存続期間を10年と定め、この間に使用されなくなった商標(不使用商標)を整理する(権利を失わせる)一方、 信用が蓄積し、使用され続けている商標については、10年を経過した後も、何度でも更新申請をくり返せることとし、永久的に権利を存続できるようにしています。
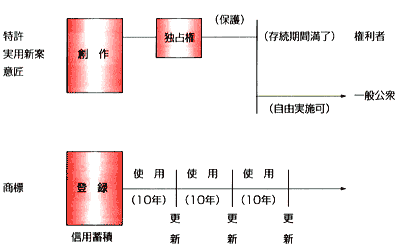
-
商標法の保護対象
商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状によって構成されるもので、これらを単独で用いたり、組み合わせて用いたり、 あるいは色彩と結びつけた標章(マーク)であって、業者がその商品又は役務について使用する標章をいいます。 平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

特許法、実用新案法、意匠法の3法が、人間の創造的活動の成果である「創作」を保護することを目的とするのに対して、 商標は、それ自体として創造性を必要とするものではなく、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを直接の目的としています。 このように目的が大きくちがうため、商標制度の仕組みは、他の3つの制度と色々な点で異なっています。

